保育のお仕事
保育園の1年間の行事について
保育園では1年を通してさまざまな行事やイベントがあります。
行事の計画と実行も、保育士の仕事となります。年間のイベントや行事が多いため、多くの保育士はアイディアが出てこないなど様々な理由で苦しんでいます。今回は、保育園の行事について詳しくご説明します。
ねらいを理解することで、1つ1つの保育園の行事に対する気持ちが変わるかもしれません。
保育園で行われている行事をまずはみてみよう!

まずは年間を通して行われる、保育園の行事でどのようなものがあるのか見ていきましょう。園の保育方針により年間の行事内容は変わってくる可能性があるため、主な保育園で行われる行事やイベントの一例をご紹介します。
(毎月行われているお誕生日会の記事はこちらをクリック。)
春(4月~5月)の保育園の行事とは
?4月:入園式、親子遠足
?5月:こどもの日、母の日
夏(6月~8月)の保育園の行事とは
6月:父の日
7月:七夕、プール開き、お泊り保育、夏祭り
8月:プール遊び、夏休み
秋(9月~11月)の保育園の行事とは
9月:敬老の日、お月見、秋の遠足
10月:ハロウィン、運動会、芋ほり大会
11月:七五三、作品展
冬(12月~3月)の保育園の行事とは
12月:クリスマス
1月:お餅つき大会、お正月遊び
2月:豆まき、生活発表会(おゆうぎ会)
3月:卒園式(お別れ会)、ひなまつり、お別れ遠足
保育園で行事を行うねらいは?
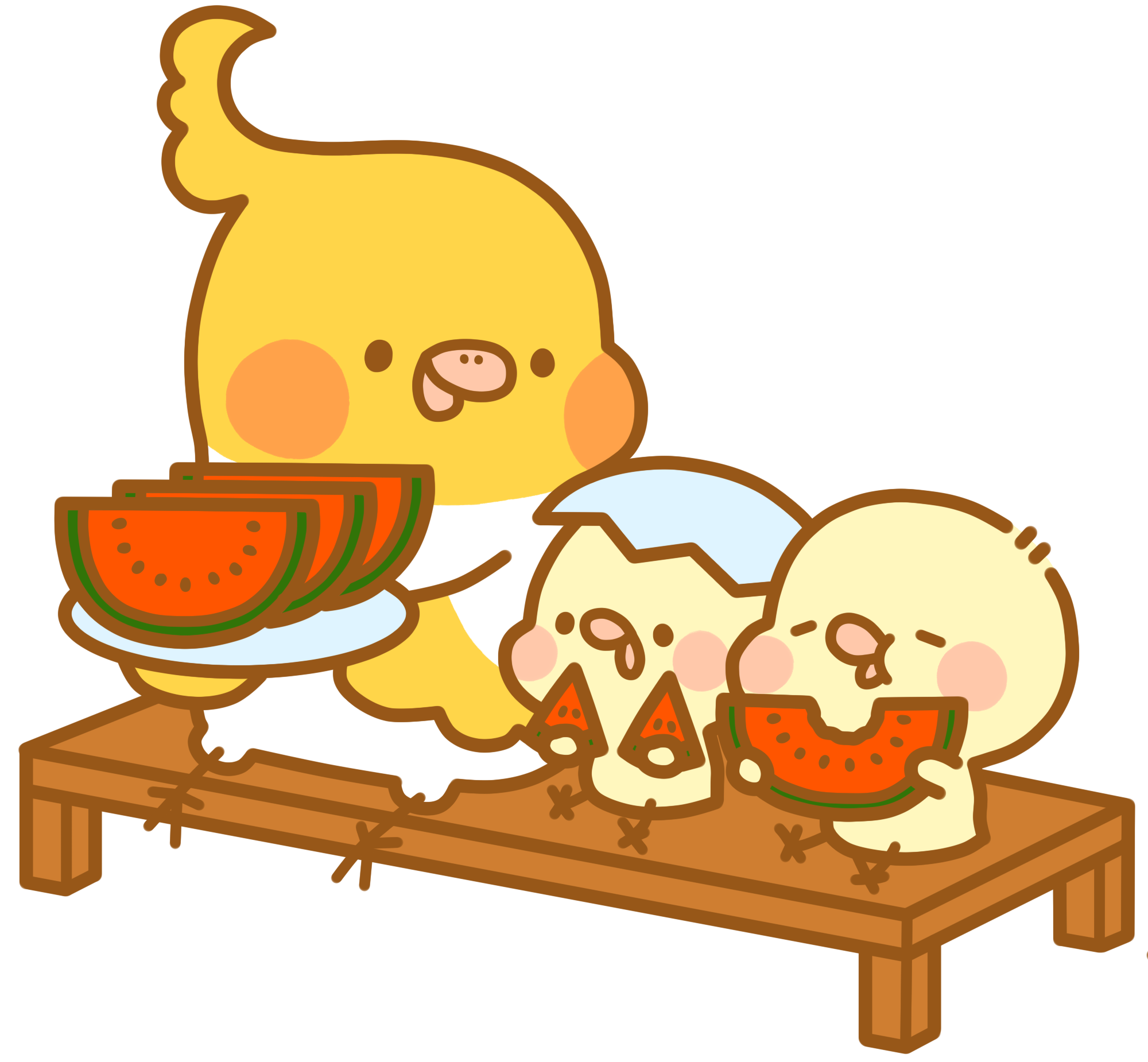
保育園でおこなう行事のねらいは、どんなものがあるでしょうか?それぞれの行事のねらいを、特徴をふまえてご紹介します。
入園式、卒園式(お別れ会)の狙いとは
4月に行う入園式と3月に行う卒園式の紹介です。
この2つは、「子どもたちの成長の節目」に行う行事ですね。
<入園式と卒園式のねらい>
〇入園式
入園式は新年度の、一番最初に行う行事となります。保育士の紹介とともに、入園する子どもたちを迎えます。4月は新しく入園した子どもたちにとって、家族以外と過ごす初めての経験がいよいよスタートする月です。緊張や不安のなか、在園児とともに、新しい生活への期待感を高めることができます。
〇卒園式(お別れ会)
保育園でのさまざまな思い出を振り返り、自身の成長の実感を感じることができ、小学校に進級するための期待感や自信を、子どもたちにもたせることもできます。祝福のことばをうけて、在園児や保護者や保育士に対して、感謝の気持ちをもつ機会にもなることでしょう。
運動会の狙いとは
保育園の一大イベントのひとつは、運動会です。運動会のねらいは、子どもたちが日頃の練習の成果を披露する楽しさや高揚感、お友だちと協力して、一つの目標へ向かう楽しさや達成感を知ってもらうことです。
そして、運動会は保護者にとっても、子どもの成長を見ることが、絶好の機会となる、大事な行事といえるでしょう。
生活発表会やお遊戯会のねらいとは
生活発表会は、子どもたちの年齢にあった出し物を発表することで、1つのことに一生懸命取り組み、最後まで成し遂げることで、達成することへの喜びを感じてもらうことができます。保護者は、保育園で過ごす子どもの様子を見る機会はほとんどありません。
ですから、生活発表会の大きなねらいは、子どもたちに、歌やダンス、劇などさまざまな形で成長を披露してもらうことだと考えられます。
遠足、お泊り保育の狙いとは
普段とは違った環境で保育をすることで、日常では得られない経験ができ、成長に必要な要素を身につけることができます。
遠足のねらいとは
遠足にはさまざまな種類があり、それぞれにきちんとしたねらいがあります。
季節の節目に行う遠足は、「季節の移り変わりを感じ、子ども同士の親睦を深めること」
親子遠足では、「親子の思い出作りと、保護者同士の交流の場をつくること」
お別れ遠足では、「卒園児に、今までの園での遠足の思い出を振り返り、成長を実感する」
あえて園外で行う遠足は、公共のマナーを学べて自然とも触れ合えるので、子どもたちの成長に必要な園の行事といえます。
お泊り保育のねらいとは
いつもと違う環境で、寝泊まりをするお泊り保育は、家族から離れて、お友だちや保育士と1日を過ごすことで、自立心と協調性を身に付けることへつながります。
歴史や文化にふれる
日本や海外の行事を保育で取り入れている理由は、子どもたちに日本の文化を身近に感じてもらい、親しみをもってもらうといったねらいがあげられます。
保育園では、こういった行事のたびに、その行事にちなんだものを、折り紙やねんど、段ボールなどを使って創作を行っています。
そうすることで、子どもたちの想像力を豊かにし、イメージを表現する力を育むことができるのです。
ですから、こういった日本の文化を行事に取り入れることは、子どもたちは、日本の歴史や伝統にふれ、子どもの成長に必要な力を同時に得ることができるので、一石二鳥の保育ができる方法だといえるでしょう。
保育士が行事を行う上で気を付けることは?

行事の目的やねらいを、間違えてとらえてしまっては、せっかくの行事を子どもたちのために生かせません。
保育士は、行事の由来や意味、子どもたちにどんな影響を与えるかなど、行事に対するねらいを明確にし、行事に臨むことが必要です。
行事は子どもたちにとって大切なもの
保育園を卒園すると、園児は年間のイベントや行事を学ぶ機会を徐々に失っていきます。
そのため、園で行う行事やイベントの経験は、子どもたちの一生でかけがえのないものになります。
保育園に行事があることで保育士の負担が増しますが、子ども達の経験や成長を行事やイベントを通して感じることができ、保育士としてのやりがいを感じる瞬間になります。保育士にとって毎年恒例の行事になるかもしれませんが、園児やそのクラスでは一回だけです。
子ども達や保育士、保護者にも楽しく好印象が残る行事にしましょう。
2024/08/26

